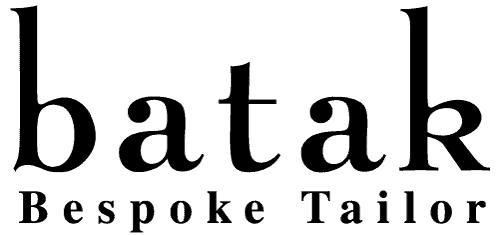小津 安二郎 監督作品「彼岸花」(1958年・松竹配給)の中で、主人公を演じるモーニング・コート姿の佐分利 信が、新郎新婦に向けての祝辞を述べる場面があります。画面に映し出される端正なヘアスタイルに貫禄たっぷりな風貌。ちょっとしたユーモアを交えながら場の空気を和ませられる大手企業の常務。演じる佐分利の立体的なキャラクターには、えも言われぬ凄みが漂い、映画の観客を嫌が応にも列席者にしてしまいます。晩年の小津作品には共通して、場面場面に奥行きを感じさせる作り込みがある、と多くの映画ファンが指摘します。同じ作品を繰り返し観ても観客を飽きさせない理由がそこにあるのでしょうか。なにゆえに、観客である私たちは小津の映画に引き込まれるのでしょうか。多くの小津ファンや批評家が述べているように、当時の作品にはお洒落な大人の立ち振る舞いや所作が散りばめられている、という指摘は正鵠を射ています。例えば、料亭で食事をするシーンです。酒の注ぎ方や箸の置き方を観ていると、一つ一つの所作に無駄がありません。また、テーブルの上に置かれたスカッチウイスキーの銘柄など、一途な精緻さが伝わってくるから不思議です。同様に、私たちがテーラーであるがゆえに、劇中の服装から漂う大人の所作には厳しい眼差しをもって鑑賞しているにもかかわらず、役柄と装いにまったく破綻がありません。戦後〜昭和30年代の決して社会が豊かではない時代を感じさせぬ美意識とセンスには驚きを覚えます。小津映画といえば、3ピースの背広を思い浮かべる観客も少なくありません。華奢で平板な体型が当たり前であり、戦前・戦後を通じて「動きやすい」ことこそが背広の選択尺度の主要因だった時代に、背広を着たときの所作で日本的なモダニズム(欧米化)を表すアイディアは小津の個人的な嗜好に拠るところが大きいと想像できます。たとえば、晩年の作品「秋日和」(1960年・松竹配給)の佐分利信、中村伸郎、北龍二の各キャラクターを各々が着る3者3様の背広とその所作で表している点です。東京大学で同窓だった3人の主人公。先に亡くなった親友の七回忌の席から映画は始まりますが、3人ともに黒の略喪服を着ていません。恰幅(かっぷく)のいい佐分利はモヘアの光沢があるシャドーストライプのグレイシャークスキン。華奢な中村はストライプがある薄茶のウールモヘアらしい背広。体躯を稼ぐための補正が随所に施されています。そして、北が着るのはダークグレイのマットウース。かなりヘビーなウエイト。合わせるのは間隔の空いた同系色のドットのネクタイ。いずれの背広も注文仕立てで、吊し(既製品)ではありません。なぜなら、3人ともに社会的地位の高いポジションの役柄であると同時に、昭和35年と言えばまだ背広は誂えるのが半ば常識だった時代だからです。会社の重役である佐分利の堂々とした背広に帽子を被る姿は人格の重さを表現しています。一方、背広に「着られている感」のある中村は、頭がいいのだが、軽はずみなところがあるキャラクター。どことなく背広が板についていません。そこにキャラクターのスキを感じさせるのです。モヘア系の他の二人と対比するように、ビジネスマンとは異なる落ち着いた品格をアンダーステイトさで表現したのが北の役柄でしょうか。大学教授で学究肌の真面目人間。ダークグレイの背広が板につています。このように、役者や女優が着る背広や衣裳を観ているだけでも楽めるのが、小津映画の一つの魅力とも言えます。小津監督本人が衣服に対して格別のこだわりと愛着をもっていたことは、自分用に襟のカタチを誂えた白いシャツを一時に9枚もオーダーしていたことからも容易に想像できます。背広に関しても贔屓のテーラーを抱え、流行を意識しながら注文のタイミングを見計らっていたこともファンのみならず多くが知るところです。もっとも、背広とは誂えるものという概念が常識だった時代ですので、小津監督自身が背広に一家言持つのも自然なことかもしれません。昭和30年代前後と言えば、ネクタイを締め背広を着て仕事に就く人は日本の就労人口の約40%(平成ですと85%)しかいませんでしたから、ホワイトカラーの生活と日本のモダニズムが連動して描かれているのも不思議ではありません。ところで、「秋日和」では主役の3人ともシャツは揃って白を着ていました。ホワイトカラーゆえなのでしょうか、小津の白シャツ趣味なのかわかりませんが、仕立てと生地の質のいい白いシャツは、成熟した大人の男を感じさせるものです。(バタク スタッフ長澤)

「彼岸花」/1958年公開/キャスト:佐分利信・有馬稲子・山本富士子・佐田啓二他/松竹映画配給
「秋日和」/1960年公開/キャスト:佐分利信・原節子・司葉子・中村伸郎・北竜二他/松竹映画配給