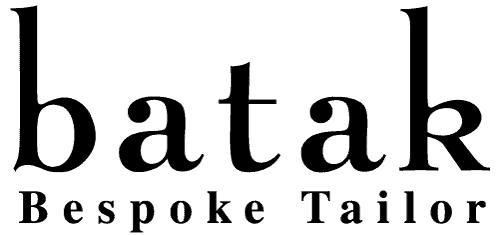GQ誌により20世紀における最高のスーツであると賞賛されたのが、映画「北北西に進路を取れ」で主演のケーリー・グラントが着たあのスーツです。映画業界・ファッション業界のみならず、スーツを日常着とするビジネスマンの世界でもこのスーツについて賞賛を述べる人は少なくありません。バタクでもこのスーツを範にしたいというビスポークのオーダーを数多く受注してまいりました。では、なぜ、ケーリー・グラントが着たグレイのグレンチェック・スーツが人々を魅了するのでしょうか。また、メンズ・ウエア史に多大な影響を与えたと欧米のメディアが指摘する理由はどこにあるのでしょうか。テイラーの視点で探っていきたいと思います。
—仕立てはサヴィルロウ—
まず、件のグレイ・スーツを仕立てたのはどこのテイラーだったのでしょうか。欧米のメディアの見解では、サヴィルロウの「ノートン&サンズ」(注1)、同じくサヴィルロウの「キルガー フレンチ&スタンバリー」(注2)、さらにビバリーヒルズのデザイナー「クエンティーノ」の名前が上がっています。この中で、ホテルのシーンについては「クエンティーノ」のラベルが認識できますが、これを「キルガー」は否定し、自店が手掛けたと主張しています。実はこのホテル・シーンのスーツ、つまりあの有名な軽飛行機に追われる時に着ていたスーツは他のシーンのスーツと微妙に違うことにお気づきでしょうか。作中2パターンのカットが確認できることから、いくつかのテイラーがかかわっていたのかもしれません。ちなみに「キルガー」はケーリー・グラントのパーソナル・テイラーであり、直線的なカットを得意としていました。また、当時、グラントが影響を受けていたといわれるウインザー公のテイラーのひとつでもあり、公を担当していた「キルガー」のアーサー・ライオンというカッターがグラントも担当していたと言います。
注1:「ヴァニティフェア」誌の見解
注2:「GQ」誌の見解
— 英米混成のミッドセンチュリー・ルック—
「キルガー」の仕立てだと仮定した場合、サヴィルロウのスーツでありながら英国的なスタイルとは言いがたいカットをどう解釈すればいいのでしょうか。実はケーリー・グラント、作品や役柄のキャラクターは違っても、この時期に着ているスーツはいずれも非常に類似性の高いカットなのです。しかも、作品やキャラクターに合わせて非常に細かな微調整を施しています。太いトラウザーズに50年代にアメリカを席巻したボールドルックの特長が反映されてはいるものの、上衣はと言えばフィットした構築的なブリティッシュ・スタイルで、50年代後半から流行り始めるナチュラル・ルックのニュアンスも色濃く持ちあわせているのです。やはり、世界の市場をターゲットにしているハリウッド映画であり、舞台はアメリカ・ニューヨークということを考えると、英国スタイルというよりもニューヨーカー的なビジネス・スーツが求められたのでしょう。
— 役柄に合わせた、微妙なドレープの調整—
彼の当時のスーツスタイルの特長は、「長い着丈」「肩に少々のパッド」「シングルの3ボタン段返り」「ゆったりとした太めのトラウザーズ」「絞り量の少ないウエスト」などですが、役柄に合わせて微妙にラペルの幅を変化させたり、肩パッド量を増減したり、上着のゆとり量を調整したりしています。「噂の名医(‘51年)」あたりから、スーツに興味がない人が見ても何となくグラント風とわかるこのスタイルは、「泥棒成金(’55年)」「めぐり逢い(’57年)」「月夜の出来事(’58年)」そして「北北西に進路を取れ(’59年)」まで続くわけです。どのように役柄に合わせて調整しているかというと、「泥棒成金」や「めぐり逢い」の主人公のように働かなくても悠々自適な暮らしをしているキャラクターには、胸から肩にかけてのドレープの余裕をたっぷり取り、ゆったりとした優雅な雰囲気に仕上げます。片や「北北西に進路を取れ」のニューヨークで広告業を営む主人公が着るスーツは、ビジネスマンらしさを演出するために、胸から肩にかけてのドレープを抑えてアクティブな雰囲気に仕立てていることが見て取れます。このような微妙なドレープによるフィッティング調整のアイディアは、キャラクターに対する徹底したこだわりとリアルな人物を描く深い洞察、高度な仕立て技術がなければ中々成立するものではありません。
—変わるアメリカ社会—
「北北西に進路を取れ」のスーツが素晴らしいのは、’50年代という時代がもたらした社会的かつ文化的な変革を投影している点にもあると思われます。戦後の’40年代から続く華美なメンズ・スタイルの潮流が、簡素化へ向かう’50年代後半。クルマが大衆に普及し、自動車通勤の増加によって郊外生活が生まれ、石油製品(プラスチックや化学繊維)の登場により規格大量生産の商品が当たり前の存在になります。当然、この映画の舞台となる’50年代の終わり頃から注文服(ビスポーク)も既製服にとって代わられ、この流れは’60年代初頭のより簡素化が進んだミニマル・スタイル(グラントはサヴィルロウ仕立てのサックスーツでこれを表現)へと移っていくわけです。ケーリー・グラントの’50年代の10年間に各作品共通のスタイルで通したスーツが魅力的に映るのは、おそらくこうした時代の変革と呼応してビスポーク=誂える文化が最後の輝きを放ったからではないでしょうか。しかも、アメリカというサヴィルロウのビジネスを支えている、新たな大市場を予感されるシンボリックな存在に思えたのかもしれません。