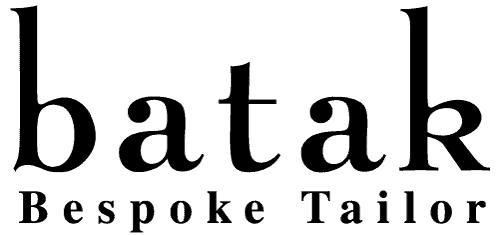日本ではまだテレビなどの情報メディアがほとんど発達していなかった‘50年代。紳士服のスタイルに関する情報源は、映画ぐらいしかなかった時代である。「カッター&テーラー」のような業界向け専門誌を海外から取り寄せてはいたものの、その内容は服づくりの情報に傾倒していて、専門職であるテーラーでさえ、なかなか本場のリアルなスタイルを把握することはできなかった。
そんな折り、ロンドンのマーチャント「ドミール・フレア商会」(現在は廃業?)の極東総支配人が、1953年に来日している。好機にとばかりに、日本のテーラー業界の団体は、同商会の支配人を囲む晩餐会を帝国ホテルで催している。集ったテーラーたちの最大の興味は、「今、ロンドンはどうなっているのか?」、「欧州で幅を利かせているスタイルはどんなものなのか?」だったそうだ。
宴会でまず話題に上ったのは、スーツのスタイルである。戦後はアメリカ映画に登場した身体を大きく見せる「ボールド・ルック」が日本を席巻していたが、ロンドンはどうやら違っていた。
「アメリカでは肩幅が広く、大胆に太いトラウザース・スタイルが流行していますが、ロンドンでは地味な志向がもてはやされています。言い換えれば、昔風の英国スタイルです」(ドミール・フレア商会 W.F.ペシエ)。
上着は身体にフィットし、袖口は細く、トラウザースは程良い太さ(現代よりもかなり太め)。ウエストコートは小さな襟付きのものが主流だった。英国人は90%がウエストコート付をオーダーし、ダブル・ブレストの場合も同様だという。色柄についてはどうだろう。「ロンドンでいま人気のある柄は、細かなピンヘッド、細いヘリンボーン、細いグレンチェック、細いピンストライプ。派手な柄や幅の広いストライプ柄は好まれていません」(ドミール・フレア商会 W.F.ペシエ)。どうやら、「細い/ナロウ」がキーワードだったらしい。現在に通ずる端正な柄が好まれていたことが見受けられる。注文が多い色柄は、仕事にも遊びにも兼用できる色合い。つまり、仕事から帰宅して遊びに行くのに着替えて出かけていかなくてもいい色柄である。具体的にはグレーやネイビーがもっとも多く、ブルー・グレーがそれに次ぐという話だったらしい。こうした支配人による当時の話を総合すると、一部を除いて現代の志向に近く、渋めの男のイメージであったことがわかる。‘40年代や’60年代スタイルを下敷きにビスポークされるカスタマーは多いが、’‘50年代スタイルとなると捉えどころが少ないせいか、注文する方はぐっと少なくなる。しかし、40歳代以後のちょっと野暮な感じも“こなせる”ようになった方には、是非オススメしたい。たとえば、「北北西に進路を取れ」(’57年)や「泥棒成金」(’54年)でケーリー・グラントが演じたミドル・エイジならではの大人っぽい雰囲気を——。